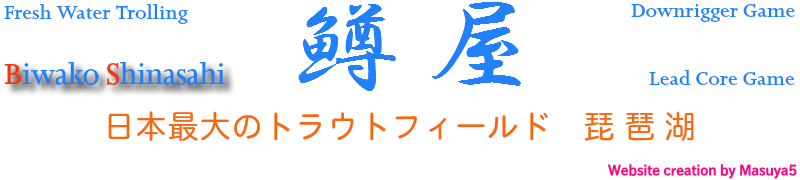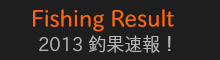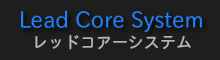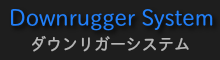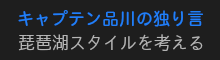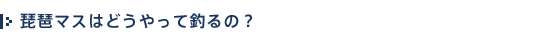
琵琶マスをレイクトローリングで狙う場合、大きく分けて二通りの釣り方があります。
一つは、「レッドコアーシステム」、そしてもう一つが、「ダウンリガーシステム」です。
もっとも、この二通りの釣り方は各々別々に釣るわけではなく、一艇のボートで効率よく併用しながら釣りをします。
それでは「レッドコアーシステム」と「ダウンリガーシステム」の個別の説明をしていきます。
レッドコアーシステム
レッドコアライン
 中心に鉛線が入り、ダクロン(従来)又は、PEで編みこんだラインを使用し、ラインを長く出すことで深く沈めます。
中心に鉛線が入り、ダクロン(従来)又は、PEで編みこんだラインを使用し、ラインを長く出すことで深く沈めます。
このレッドコアラインを用いて、水面付近から水深20mまでを狙います。太さと重さの違いをポンドテストで表示しています。
市販されているもので、12lb・15lb・18lb・27lb・・・と有り、沈下スピードは同じメーカーの場合同じと表示されています。
グデブロッド社には、鉛の入っていないノンレッドのものも有ります。
100yd(91m)基準で作られ、連結スプールで売られているものもあります。 10yd毎に色が付いていて、舟速何kmで、何色で何m沈むと記されていますが、実際には波や風、流れの問題が有り、自分が釣りをする現場でテストしてみるとよいでしょう。
琵琶湖でのお勧めは、18lbタイプ、100ydです。湖流の無い湾で、グデブロッド18lb、リーダーフロロ5号8m、2/0ドジャー、自舟速度 3kmで、水面にラインエンドを浸け、100ydで、水深9.5mで、底にドジャーが当ります。15lb・12lbでは当りません。ティムコ社の18lbは、もう少し深く沈みます。
ロッド
短い程取り回しが楽ですが、長いロッドの方が竿のタメが有り、ダウンリガーとのコンビネーションには、有利です。
実際には、短くて8’6”〜9’6”。 ロングロッドでは、12ft。ダウンリガーを併用しない場合や、舟が20ft以上有る場合は10ftが良いと 思います。
リール
ABU7000クラス、ギア比があまり早いものはバレやすい。又、使えるならシンクロモデルが良いと思います。
ラインを100yd以上出すことも多く、頻繁にリールを巻くので、電動リール「シマノブレイズ3000クラス」を使っています。
ライン
ナイロンの太めのもので下巻きを20〜30m。PE2号を100m。メインラインとして、PEカバーレッドコア100yd、又は18ibノーマルレッドコア100yd。リーダーは、フロロカーボン5号8m。
PEカバーレッドコアは、従来のレッドコアラインに比べ、約2倍の沈下能力が有り、100yd+10m又は20mで水深20mを狙う事も可能です。
ノーマルレッドコア100yd、2/0ドジャーを付けたとき、舟速3kmで、約9m沈んでいますがバッキングPEを30m出すことで15mまで沈められます。
リーダーはランディングを考えロッド長の2倍+せっかく沈めたいのでリーダーを長くとりすぎるとルアーを浮かすことになりかねない。
ダウンリガーシステム
 ダウンリガーと呼ばれている、大きな重りを水中に入れ、確実に一定の棚に仕掛けを入れておく装備。
ダウンリガーと呼ばれている、大きな重りを水中に入れ、確実に一定の棚に仕掛けを入れておく装備。
道具立ても多くて重く、たいそうな物で、20年前にも何回か使いましたが、サクラやサツキを釣るには、レッドコアラインと比べあまりメリットを感じなかったのですが、深い棚でもヒット率の高い琵琶鱒トローリングには、かなり有効なタックルです。
又、初心者からベテランまで、ランディング(取り込み)が非常に楽です。
手巻上げと、電動タイプと手作りがありますが、どういう釣り方を目指すかで選択します。
アメリカ製のキャノン、カナダ製のスコッティーや、ウォーカー、マイボートの方には、スコッティーの電動がお勧めです。
レンタルボートを使う場合は、大きさ重さ、電力消費量を考えれば、ウォーカーEDR-2のスイベルマウント付きがお勧めです。
又、ちょっとやってみたい方には、スコッティー1050、1060や、ウォーカーキングフィッシャーがお勧めです。
1ダウンリガー1ロッドと2ロッドのシステムが有り、1ダウンリガーで2ロッドの場合、水圧抵抗を考えウエイトは重めにします。